市町村民税非課税世帯、多子世帯、ひとり親世帯等の利用者負担額(保育料)軽減制度
0歳児から2歳児のうち、1.市町村民税非課税世帯、2.多子世帯、3.ひとり親世帯等の利用者負担額(保育料)について、以下のとおり軽減制度があります。
1.市町村民税非課税世帯
保育料は無償です。
ただし、父母(ひとり親も含む)が非課税かつ収入が一定基準を下回る場合は、同居の家族を算定対象に含める場合があります。
2.多子世帯
保育所、認定こども園(2、3号認定)、小規模保育施設、家庭的保育施設等に在籍する児童に生計を同一にする(注意1)兄姉がいる場合、兄姉の年齢に係わらず、年齢の高い順に数え、当該園児が何人目のお子様かにより、以下のとおり保育料が軽減されます。
| 要件1 算定対象となる世帯の税額要件 |
要件2 施設利用している園児にかかる要件 |
軽減割合 |
|---|---|---|
| 所得制限なし | 同時に在園する園児(注意2)が2人おり、当該園児が2人目の場合 | 半額 |
| 同時に在園する園児(注意2)が3人以上おり、当該園児が3人目以降の場合 | 免除 | |
| 市(町村)民税所得割額57,700円未満の世帯 | 園児が、生計を同一にしている子どものうち2人目の場合 | 半額 |
| 園児が、生計を同一にしている子どものうち3人目以降の場合 | 免除 | |
| 市(町村)民税所得割額97,000円未満の世帯 | 園児が、生計を同一にしている(注意1)子どものうち、3人目以降に該当する場合 | 免除 |
注意1:兄姉の年齢は問わず、同居(住民票が同一住所地)している子ども、または、別居(住民票が別住所地)であっても、生計を一にしている実態が確認できる子ども。
例:就学や療養等の都合上、別居(住民票が別住所にある)しているお子様について、生活費や療育費の仕送りが定期的に行われている場合は、生計を同一にしている子どもに該当します。なお、お子様が婚姻されている場合やひとり暮らしで独立されている場合は、含みません。
注意2:同時に在園する園児とは、保育所・幼稚園・認定こども園・企業主導型保育施設・特別保育施設・特別支援学校幼稚園部等に通所若しくは通園し、家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業等による保育を受け、または児童発達支援もしくは医療型児童発達支援を利用している就学前子どもをいう。
3.ひとり親世帯等
ひとり親世帯等(注意2)において、保育所、認定こども園(2、3号認定)、小規模保育施設、家庭的保育施設等に在籍する児童のうち以下に該当する場合には軽減が適用されます。
| 要件1 算定対象となる世帯の税額要件 |
要件2 施設利用している園児にかかる要件 |
軽減割合 |
|---|---|---|
| 市(町村)民税所得割額77,101円未満の世帯 | ひとり親世帯等であって、園児が1人目の子どもの場合 | 軽減 注意:保育料表(C1、D1、D3、D5)のとおり |
| ひとり親世帯等であって、園児が、生計を同一にしている子どものうち2人目の場合 | 免除 | |
| ひとり親世帯等であって、園児が、生計を同一にしている子どものうち3人目以降の場合 | 免除 |
注意2:
ア)母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。
イ)身体障害者手帳または療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者並びに特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯
なお、兄姉が同時に在園されている場合、在園児の2人目は半額、3人目は免除となります。
この記事に関する
お問い合わせ先
子ども未来局 保育幼稚園課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305
保育幼稚園課にメールを送る
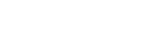

























更新日:2023年02月14日