市長記者会見(令和7年2月7日)
- 日時 令和7年2月7日(金曜)13時から
- 場所 大津市役所 新館2階 災害対策室

市長説明
市長 皆さん、こんにちは。お忙しい中、市政記者クラブの皆様には定例記者会見にご出席いただき、誠にありがとうございます。
それでは、私からお手元のパワーポイントの資料1に沿ってご説明申し上げます。

まずは概要について申し上げます。
令和7年度当初予算案は、大津市総合計画の基本構想に掲げます3つの基本方針に沿って編成するとともに、教育環境の充実など、総合計画第2期実行計画でリーディングプロジェクトとしていた事業につきましても、その効果を最大化するため、継続的・発展的に進めてまいります。
また、いよいよ令和7年度に開催されます「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」に係る経費のほか、保育所等の待機児童への対応や不登校対策、防災対策、物価高への生活支援など、喫緊の課題への対応にも意を用いたところです。

それでは、各会計の予算額について申し上げます。
一般会計の総額は1,463億8,400万円で、当初予算としては過去最大です。前年度と比較しますと5.8%、80億1,300万円の増加となります。特別会計は8会計で総額778億6,400万円、特別会計は11億円余りの増加。増加の主な要因としては、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計での医療費の増加や、介護保険事業特別会計でのサービス給付費等の増加によるものです。企業会計は3つの会計を合計して351億4,000万円余りで、3億4,000万円の減少。全12会計では2,593億8,800万円となります。
続いて歳入です。一般会計の歳入のうち、個人市民税で個人所得や納税義務者数の伸びによる23億7,900万円の増額見込みをはじめ、法人市民税では好調な企業業績を、固定資産税ではマンション・住宅の新増築や企業の設備投資の増加を反映して、市税全体で前年度を33億3,900万円上回ると見込んでいます。なお、地方特例交付金が大きく減少しておりますのは、定額減税の減収補塡分がなくなったためです。
また、ここには記載されておりませんけれども、基金からの繰入れにつきましては、財政調整基金から約19億5,000万円、このうち国スポ・障スポ分として13億9,000万円を取り崩すとともに、公共施設等整備基金から8億3,400万円を繰り入れております。
一般会計における歳出につきましては、上段の目的別で見ますと、総務費の増加は国スポ・障スポの開催や自治体情報システムの標準化への対応によるもの、民生費の増加は社会保障関連経費が中心で、介護・障害福祉サービスの利用増、児童手当の拡充、公定価格の引上げによる民間保育施設への施設型給付等の影響が大きくなっています。衛生費は帯状疱疹ワクチンや新型コロナウイルスワクチン等の予防接種に係る経費などにより、土木費は市道や都市計画道路等の整備の進捗に伴って増額、教育費は学校施設の長寿命化改良、中学校体育館への空調設備設置などのハード面の整備により増加しています。
下段の性質別では、人件費が定年延長による退職手当の隔年化による減があるものの、人事院勧告に基づく給与改定などにより10億4,700万円の増、4.1%の伸びとなっています。
財政調整基金からの繰入れを行い、編成はしているものの、特に国スポ・障スポの経費の見合い分などは、令和7年度の開催を見通して、これまで計画的に積み立ててきたものを取り崩しており、全体を通して適切に財政運営がなされているものと捉えています。
一方で、少子高齢化の進展からある程度増嵩を見込んでおりました扶助費や公共施設の老朽化への対応だけでも財政負担が大きい中にあって、この急激な物価や人件費の上昇が与える影響には、より一層注意を払う必要があると考えています。
引き続き、国や県からのものも含め財源確保を図るとともに、事業の有効性・必要性を精査することで、健全財政の堅持に努めてまいります。
それでは、予算編成の方針に沿って取り組む主な事業についてご説明いたします。大変細かい事業もありますので、かいつまんだ説明になりますが、よろしくお願いします。

子育て支援では、妊婦をはじめ子どもや保護者に寄り添う視点で切れ目のない支援を図るとともに、子どもを産み育てやすい環境づくりを進めます。
まず、待機児童・保育士確保対策です。
今年度、小規模保育施設2カ所の整備を図ったところですが、令和7年度につきましても、宅地開発等によって就学前児童が増加している中北部地域に保育施設の整備を行うため、民間保育施設の整備補助事業に取り組みます。
保育士等奨学金返還支援事業費補助金につきましては、本年度既に補正予算で措置しているところですが、引き続き、市内の保育所等で勤務する保育士が奨学金を返還している場合に、その一部を補助します。
潜在保育士等就職支援給付金も今年度補正予算で措置した事業の継続であります。引き続き、潜在保育士の保育現場への復帰を促してまいります。
保育士等処遇改善費補助金につきましては、市内の民間保育所等における職員の確保と継続的な就業を支援するため、市の独自事業として補助を行っているものであります。
また、保育士確保に向けたPR事業に取り組みたいと思っています。保育士の仕事の魅力や大津市内の保育所等をPRする冊子をリニューアルするとともに、広く配布することとしております。
次に、妊産婦支援と子どもの育ちへの支援です。
妊婦健康診査につきましては、今年度から受診券による助成額を超えた自己負担分を無料化しており、引き続き、出産に係る経済的負担を軽減し、必要な健康診査を適切な回数受けることができるよう支援してまいります。
産後ケア事業につきましては、1回の分娩に対して最大7回まで利用できるようになっていますが、令和7年度からは新たに居宅訪問事業について初回利用料を無料とするとともに、利用料の一部を減免し、より産後ケアを利用しやすい環境を整えてまいります。

乳幼児健診事業につきましては、現在、4カ月から3歳6カ月までの間に5つの健診を実施しておりますが、令和7年度からは新たに1カ月児健診を追加することで、発育状況のきめ細かい確認や疾病の早期発見につなげていきます。
また、令和7年度の組織機構改革におきまして、新たにこども総合支援局を設けることとしておりますが、これに合わせて全ての子どもの健康増進と発達を支援する「大津方式」の仕組みを時代のニーズに合わせてアップデートし、妊娠期から学齢期まで切れ目のない子どもの育ちの支援に努めてまいります。令和7年度は、新たに支援に必要な情報を庁内関係所属で共有するためのシステムの改修を予定しています。
次に、子どもの貧困の解消に向けた学習・生活支援です。
子どもやその家庭に対し、学習サポートや、子どもたちが安心して過ごせる地域の居場所づくりの支援を充実させます。
令和7年度から、大学等受験料支援事業費補助金により、児童扶養手当を受給するひとり親世帯、生活保護受給世帯を対象に、大学等受験料に係る費用を補助します。
また、子ども食堂等支援事業費補助金では、夏休みなどの長期休暇期間中の居場所づくりの拡充を目指して、新たにこの期間における取組に対する補助金を加算することとしています。
次に、放課後児童健全育成事業です。
保護者の負担軽減を図るため、欠席の連絡などを円滑に行えるスマートフォンアプリを導入するほか、令和7年度は間食費(おやつ代)の値上げを見送り、値上げ分を公費で負担します。
子どもの教育の充実では、不登校児童生徒の支援の強化や教育環境の改善などによって、子どもたちが安心して過ごし学ぶ場づくりを進めてまいります。

市内6カ所に設置している教育支援ルームウイングと共に、学校において教室に入りづらい児童生徒が自分に合ったペースで学習や生活ができる小中学校の校内ウイングの充実を図ります。
また、アウトリーチ型支援により、教育支援員と公認心理師が自宅やその周辺で面談を重ねることで、適切な支援につなげてまいります。特に令和7年度は、行き渋りが始まった小学校低学年を対象としたアウトリーチ型支援を拡充します。
こうした市の取組の上で、子どもやその保護者を真ん中に置いて、フリースクールなどの民間施設や団体との連携を強化させます。令和7年度に、学校とフリースクールなどの民間施設や団体、それに教育支援センターが、それぞれの知見や資源を持ち寄って情報交換や意見交換を行うスクラム会議を設置します。また、フリースクール等から専門家による支援を求める声があったことから、フリースクールを利用している児童生徒・保護者に対して、教育支援センターの公認心理師と定期的に面談する機会を設けます。新たに設けるフリースクール等民間施設利用者支援補助金では、毎月の利用料の半額を上限1万円補助することとしています。

次に、教育環境の改善・充実についてです。
本市の学校施設は、約80%が建築後30年以上を経過するなど老朽化が顕著であり、引き続き、長寿命化改良事業に重点的に取り組んでまいります。令和2年度から年2校のペースで事業に着手しておりますが、令和7年度も新たに2校分の調査費用を盛り込み、既に着工している学校も年次的に事業に取り組んでまいります。
一方、学校トイレの改修事業につきましては、令和5年度から年4校のペースに事業を加速化させましたが、4校分の設計費用を盛り込み、子どもたちが安心して快適に学べる環境を整えます。
体育館空調設備設置事業では、まずは夏休み中も部活動を行っている中学校を先行して、今年度から2カ年をかけて整備を進めています。


学校給食につきましては、子育て世帯の生活支援を図る観点から、令和7年度も引き続き、食材値上がり分の公費負担を継続します。約2億1,800万円をかけて、給食費の値上げを行うことなく、安心安全で栄養バランスの取れた給食の提供を継続してまいります。
次に、特色ある学校づくりです。
令和3年度から開始した「学校夢づくりプロジェクト」では、各校で子どもたちの思いや発想を基に、地域の皆さんなどにご協力いただきながら、様々な取組がなされております。今年度からスタートした「企業版夢づくりプロジェクト」も継続し、中学生を対象にオープンカンパニー事業とキャリア教育ワーキング事業などを行うこととしています。
また、令和7年度の新たな取組として、「小学校水泳授業改善プロジェクト」を実施します。水難事故防止につながる「安全に浮く・泳ぐ」ための体系的な指導モデルの研究に加えて、学校プールの維持管理や専門的な水泳指導の観点から、小学校のモデル校1校で水泳授業の外部委託を行います。


次に、高齢者・障害者の福祉の充実、認知症施策の推進についてです。
総合計画第3期実行計画の重点プロジェクトに「認知症施策推進プロジェクト」を位置付けましたが、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されたことを受けて、これまで以上に認知症の正しい知識と理解を深めることが大切になっています。認知症サポーター養成講座や認知症カフェ事業はいずれも既存事業ですが、新しい認知症観の理解につながる取組が求められていると考えておりますので、内容をしっかりと深化させてまいります。
認知症普及啓発事業では、オレンジリングフォーラムなどのこれまでの取組に加え、新たに商業施設等における情報発信の機会を設けてまいります。
次に、高齢者の保健と介護予防の促進についてです。

健康寿命を延伸し、高齢者がいつまでも元気で自立した生活を送れるよう、シニア向けトレーニング教室をはじめとした通いの場の充実や、市内5カ所の「はぴすこ」、これは老人福祉センターから改称しましたけれども、ここを健康づくりの拠点とするなど、高齢者の保健と介護予防のための施策を推進します。
また、高齢者対象の定期予防接種事業として、インフルエンザや新型コロナウイルス等に加え、新たに帯状疱疹ワクチンの定期接種を実施し、接種費用の一部を助成します。また、令和7年度は、東はぴすこを改修し、令和8年4月にリニューアルオープンする予定です。
次に、人にやさしい車両導入促進事業補助金は、新たにタクシー事業者によるユニバーサルデザインタクシーの導入等を支援し、障害者だけでなく高齢者の移動時の円滑化を促進してまいります。
また、市独自の福祉人材の確保定着への支援として、資格取得に係る補助であるキャリアアップ支援補助金につきまして、介護職を対象にしたものを拡充するとともに、新たに障害福祉分野についても補助制度を設けます。

続いて、自然・歴史・文化・スポーツを重視し、多くの人が集うまちづくりについてです。
まずは、「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」は、滋賀県では昭和56年開催のびわこ国体以来、44年ぶりの開催となります。本市では19競技22種目の競技会を開催します。実行委員会への負担金約27億円を予算措置しています。
次に、大河ドラマレガシー事業についてです。大河ドラマ「光る君へ」の放送を契機とした取組により、紫式部・源氏物語ゆかりのまちとしての認知度が大きく向上したことから、引き続き、大津の幅広い文化資源を生かしてシビックプライドの醸成を図りたいと考えています。

「文学のまち大津」ブランディング強化事業につきましては、これまで、かるたの聖地としての取組や、松尾芭蕉ゆかりの地としての取組などを編み直し、令和7年度は資源の掘り起こし、また分析などを進めることとしています。この取組の先に、ユネスコ創造都市ネットワークへの加盟を目指したいと考えています。

次に、歴史を生かしたまちづくりです。
坂本城跡発掘調査成果啓発事業では、リーフレットを作成し情報発信に活用するとともに、出土した下駄や漆器等の木製品に理化学的処理を施し、遺物の状態が安定した段階で、埋蔵文化財調査センター等での公開を予定しています。
まちのにぎわい創出では、大津港周辺について、令和5年度の社会実験、今年度の官民連携による協議会の構築を踏まえて、令和7年度は恒常的なにぎわい創出に向けた活用計画を策定します。
大津の観光魅力向上にむけた取組に移ります。
新たに、大津ならではの観光コンテンツの造成を支援してまいります。一つは、富裕層を含めた訪日外国人観光客の誘客につながるもので、もう一つは、船舶等を活用した事業への補助を考えています。特に船舶等の活用につきましては、一過性のイベントではなく、恒常的な実施を計画する者に対して補助することで、琵琶湖を生かした商品造成と、将来的な事業の自走化を目指します。
MICEの誘致に向けては、先月から運用しておりますウェブサイトに加えて、令和7年度はパンフレットを制作して、さらなる誘致につなげます。
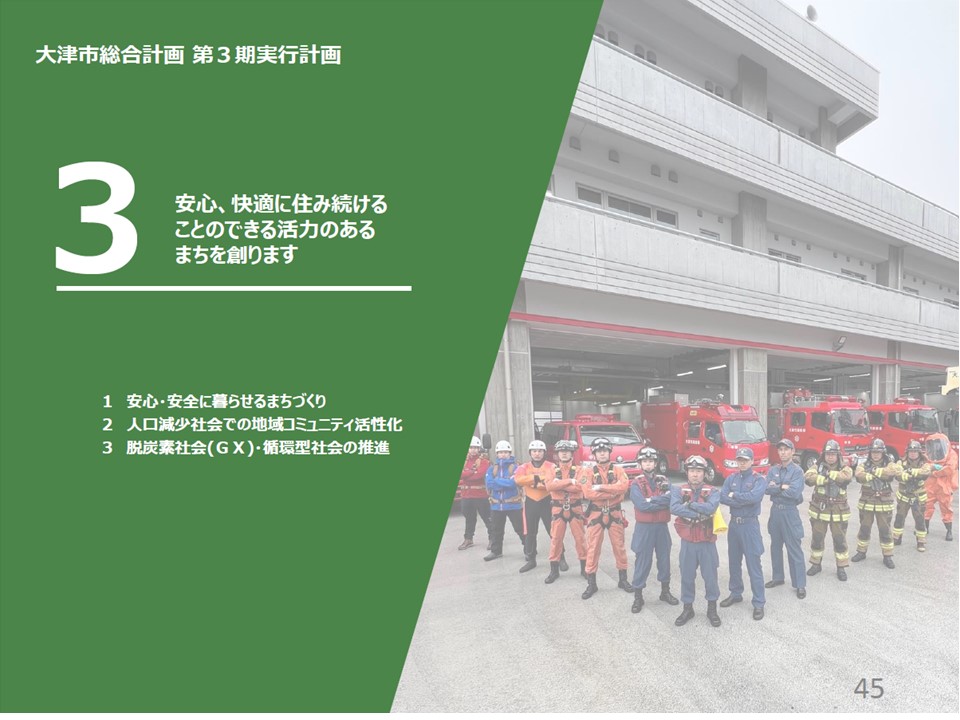
続いて、安心・快適に住み続けることのできる活力のあるまちづくりです。
市役所庁舎の整備につきましては、今年度から着手しております庁舎整備基本計画の策定と、基本設計に向けたオフィス環境調査に引き続き取り組んでまいります。
庁舎整備基本計画は、パブリックコメントを経て、令和7年度に策定を予定しておりますが、国有地の取得に向けた準備として、庁舎用地・整備用地の取得に向けた国体広場・テニスコートの解体実施設計の費用を計上しております。

次に、災害に強いまちづくりについてです。
まず、指定避難所における快適なトイレ環境の確保を図るために、新たに自走式トイレカーを導入します。また、指定避難所である小中学校の体育館等に、NTTと連携して、停電時でも使用が可能な特設公衆電話を52カ所設置します。
消防・救急体制の充実では、新たに「AED GOアプリ」を導入します。これは、ボランティア登録をされた方に、アプリを通じて心停止事案の発生と近くのAEDの設置場所を通知し、AEDの搬送と応急手当ての要請を行うものです。救急車が到着する前にAEDを活用することで、さらなる救命率向上を目指します。

次に、移住・定住の促進についてです。市内でも、周辺部において人口減少が顕著な地域が見られます。こうした地域において重点的に空き家の活用に向けたセミナーを開催するとともに、空き家バンクへの登録を促進してまいります。
次に、地域コミュニティ支援・地域交通の確保事業についてです。
総務省の集落支援員制度を活用し、葛川学区において、地域コミュニティの維持活性化に向けた取組や地域団体の運営などをサポートしてまいります。
無償運送事業補助金では、試行的に地域公共交通を補完する無償運送事業を主体的に実施する地域団体等に経費の一部を支援します。この事業を通して、地域の実情に沿った持続可能な移動手段の在り方を検討したいと考えています。
次に、DXの推進についてです。
住民ポータルアプリ、(仮称)おおつアプリは、本市のデジタル行政サービスを統合するもので、マイナンバーカードを活用し、住民一人一人に最適化された情報提供を行うとともに、市民サービスの向上を目指します。活用の一例を挙げますと、例えば避難所の受付アプリを構築することで、避難所に設置した二次元コードをスマートフォンで読み取ると、避難状況の把握が可能となります。こういった活用についても引き続き検討してまいります。
次に、GXの取組としては、市有施設の省エネルギー化を推進するため、引き続きESCO事業を活用した照明のLED化に取り組んでまいります。
次に、森林環境譲与税の活用についてであります。本市ではこれまで、森林環境譲与税を活用し、間伐や林道の維持管理などを行うとともに、担い手の確保や育成のための補助を行ってまいりました。令和7年度は、新たに森林資源の循環利用を促進する観点から、リサイクルセンター木戸を改修し、3Rの推進に加え、木工を通して啓発を図る拠点づくりを進めてまいります。

次に、物価高が続く中、暮らしを守る取組にも意を用いてまいります。令和7年度に実施いたします「おおつ割」事業では、5月中旬から事前申込みを受け付け、6月中旬に利用を開始する予定となっています。
民間保育施設や小中学校の給食については、先ほども一部申し上げましたけれども、食材値上がり分の公費負担を継続してまいります。
最後、その他の主な事業としては、終戦80年の節目の年を迎えて、次の世代に平和の大切さを伝える事業を予定しています。平和祈念展では、広島平和記念資料館の資料を、歴史博物館の企画展、瀬田国民学校絵日記展と会期を合わせて展示することとしています。また、平和祈念大津市戦没者追悼式を開催します。
まずは、私から概要の説明といたします。
質疑応答
日本経済新聞 ちょっと細かい話ですけれども、MICEのパンフレットですけれども、この間、ウェブで作って、あのときは紙じゃなくてウェブだけという話だったんですけれども、今回のパンフレットは紙で作るということですか。
市長 ウェブによって情報の発信はできるんですけれども、商談をした後に手元にしっかりと情報を残すという意味では、やはりパンフレットが必要であろうという判断になりました。
日本経済新聞 そうすると中身はウェブとほぼ同じと考えてよろしいですか。それはまた無料で配布するという形になるんでしょうか。
市長 特に商談会等で活用したいと思っています。
日本経済新聞 なるほど、観光センターとかそういうところに配るものではないと。
それから、大河ドラマは昨年に終わって、そのレガシーという話ですけれども、来年はまた滋賀県が関係する大河ドラマがありますが、これはやっぱり北のほうだから、あまり大津は関係ないという感じですか。
市長 「豊臣兄弟!」に関しては、もちろん長浜市さんが今取組を先行しているところですけれども、やはり戦国時代というのは、長浜市のみならず滋賀県内各地ゆかりのある地、またゆかりのある武将がおりますので、我々も「豊臣兄弟!」の取組についても検討していきたいと思います。
日本経済新聞 特に坂本城の辺りで関係してくるのかと思いますけれども、そのあたりも含めて坂本城をPRしていきたい、そういうお考えですか。
市長 はい。既に明智光秀のキャストも発表されたところでありますし、既に申し上げていますけれども、「豊臣兄弟!」のチーフプロデューサーにも、坂本城の発掘の成果については、直接説明をさせていただいております。
京都新聞 たくさん施策を説明されましたけれども、特に力を入れているというか、市長として肝煎りでPRしたい施策というのは、今回何になりますか。
市長 PRをするということではなく、まずは長年準備を進めてきた「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」が開催を迎える年度ですので、まずはこの国スポ・障スポを安全・円滑に開催することが、特に令和7年度の大きな使命だと思っています。その中で、冒頭申し上げたように、保育所等の待機児童への対応、不登校対策、防災対策、物価高への生活支援、こういったところは喫緊の課題でありますので、意を用いたところであります。
朝日新聞 トータル的なところで伺いたいんですけれども、今回当初としては5年連続で最大になったと思うんですけれども、先程もご説明があったとおり、社会保障の関連経費とか色々、増加の要因もあると思うんですけれども、突出してこれだけ増えたということをお聞かせ願えますか。
市長 どうしてこれだけ増えた?
朝日新聞 一番大きな要因というのは、何になりますでしょうか。
市長 一番大きな要因は、それだけやらなければいけないことが多いということだと思います。
朝日新聞 色々、計画に基づいて編成された予算案だと思うんですけれども、「新年度の予算は、ずばりこういう予算だ」とか、そういうものは言えますでしょうか。
市長 冒頭申し上げましたし、先程の質問にも答えましたけれども、一つのことだけを重点的に取り組んで、市民の皆さんの幸せはないと思っています。やはりそこは総花的になろうとも、今ある課題一つ一つにしっかりと向き合って対応していく必要があると考えています。
朝日新聞 昨年のご説明のときにも、行財政改革については不断に進めていくということをおっしゃっていたと思うんですけれども、その点について今のお考えを改めて伺えますでしょうか。
市長 これも冒頭申し上げたところですけれども、まずは国や県からの財源確保をしっかりと取り組むとともに、私たちの施策・事業についても、不断に、本当に効果的なのか、本当に意味があるものなのかということを問い直して、ここについては精査をしていく必要があると思っています。
京都新聞 今年度は大河ドラマの「光る君へ」で非常に大津市さんは注目されたと思うんですけれども、新年度予算にもレガシー事業というものが入っていますけれども、新年度の質問とはちょっとずれるかもしれませんけれども、この「光る君へ」が大津市にとってどのようなものであったかということ。今年度、結構注目の事業だったと思うので、次年度以降にどのように生かしていきたいかというところをお聞きしたいと思います。

市長 まず、先程も申し上げたとおり、大河ドラマ「光る君へ」を契機とした取組によって、大津市が紫式部ゆかりのまち、また源氏物語ゆかりのまちとしての認知度が大変向上したと思っています。
そういった中にあって、まずは今回の大河ドラマ「光る君へ」を契機とした取組によって生まれた宇治市・越前市との連携については、令和7年度も引き続き、続けていきたいと思っています。その中で、これまでの定例記者会見でも申し上げましたけれども、例えば宇治市の源氏物語ミュージアムから石山寺へいらっしゃる誘客の動線はなかったわけですけれども、こういった連携を進めることによって、同様に源氏物語、また紫式部ゆかりのまちとしての集客を図っていく。我々にとっては、文学を通したブランディングによってシビックプライドの醸成、そして全国のみならず世界への発信につなげていきたいと思っています。
京都新聞 今おっしゃっていた宇治市とかとの誘客を図るというのは、この項目でいくと資料の中に書かれていますか。またそれとは別の話ですか。
市長 資料の中には盛り込んでおりませんけれども、今年度まで活用推進協議会の取組の中で、3市で共同したホームページを設けておりましたけれども、一旦、活用推進協議会の取組は終わり、3市連携したホームページとして運用していこうと思っています。
中日新聞 待機児童対策のことでお伺いしたいんですけれども、昨年、大津市は全国の自治体で待機児童が最多になったということですけれども、今回の予算でも待機児童対策に関する事業を実施していって、来年の時点で待機児童がどうなるといいなという目標みたいなところがあればお聞かせいただきたいです。
市長 先程も令和7年度の事業として新たに民間保育施設を整備するということを申し上げました。就任以来、民間保育施設の新設というのはしておりませんでしたが、90人規模の新規園の整備に踏み切ります。こういったものを重ねながらではありますけれども、一方で昨年の出生数も減少しております。ここをしっかりと見極めながら、これからの待機児童の対策を進めていきたいと思いますが、現時点で見通しを示すことは困難だと思います。
毎日新聞 ご説明を拝聴しておりまして、子育て支援、教育の充実、高齢者・障害者福祉の充実、すごくきめ細かに、要するにドーンとイベントをやるとか、でっかい箱物を造るとかという派手な目立つ事業ではなくて、市民の生活に行き届いた、何かケアをするというような、大きい市の方針みたいなものが感じられて、そこが大きいのかなというふうに、非常に今いいなと思っているところですけれども、その辺に込められた市長の思いみたいなものがあったら聞かせてください。
市長 まずは基礎自治体として、きめ細かく市民の皆さんの暮らし、そしてまた事業者の皆さんの営みを支えていくという姿勢は、これは就任以来変わっておりませんし、この中でそれぞれの所属が市民の皆さん、また事業者の皆さんの声に耳を傾け、それに対応するということを積み上げた予算だと思っておりますので、どうしても「目玉事業は何ですか」とかということに対して、令和7年度についてはもちろん「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」の開催が一番大きい事業費を計上しているところですけれども、きめ細かく皆さんの思いに寄り添った対応ができればという思いを込めました。
毎日新聞 今の話にもありましたけれども、市長の方針が市役所のそれぞれの部署に行き渡って、その反響が戻ってきたみたいな、そういうことですか。
市長 就任してちょうど5年が経過しますけれども、今回お示しした令和7年度の当初予算案につきましても、新規という要素は非常に少のうございます。これまでの5年間の取組の中で、例えば学校の教育環境の充実とか、こういったものは継続していかなければいけないということで、やはりやらねばならぬことは既に手をつけ、そしてそれをこれからも続けていくというところの割合が高い証左だと思っています。
日本経済新聞 説明していただいた中で、船舶等を使った事業の補助がありますね。これは新たな観光コンテンツを創出するということですけれども、当然実施するのは民間なので、民間の方ともお話ししているのかなという気がするんですけれども、具体的に何かこんなコンテンツというのは、市長の頭の中にあるんですか。
市長 先程も説明の中で少し申し上げましたが、1回だけのイベントではなく、事業として1年を通じて、また季節ごとに実施していくような事業を応援することによって、それを自走化していきたいと思っています。具体的なイメージは、民間の皆さんの提案を待ちたいと思います。この時点で申し上げていいのかどうか分かりませんが、我々としても単年度としての支援ではなく、複数年度の支援というところも検討しているところです。
日本経済新聞 とすると、来年度は新規事業だけれども、単年度ではなくて、翌年度以降にも続いていくことを想定しているということですか。
市長 検討しております。
日本経済新聞 どうなんでしょう、民間からの提案ということは、何かコンペみたいなものをやって、何かアイデアを出してくださいというような、そういったことをやるんですか。
市長 コンペまでは行きませんけれども、やはり提案は広く募集して、その中で選定することとしています。
日本経済新聞 市長が就任してすぐやった水上飛行機の実験とか、面白いと思うんですけれども、あれぐらいのインパクトがあると考えていいですか。
市長 飛行機が飛ぶのと船が走るのとまた少しイメージは違いますし、どちらかというと、水上飛行機の実証飛行をやったときも、新たなる動線を作るために、事業化はやはり事業者のほうで考えていただく、その呼び水としての取組でありました。今回の船舶を活用した取組も同様でして、我々が呼び水を作ることによって、それをきっかけに新たなる事業の建て付けがなされればいいなと思っています。
日本経済新聞 その上の観光コンテンツ造成の支援、これも新たなコンテンツを作るということですけれども、こちらはMICE推進室が担当となっていますよね。だからどうなんでしょう、この観光コンテンツ造成の支援と船舶を活用した事業の補助は、ちょっと関係しているような気がするんですけれども。
市長 重なり合うところはあると思いますが、観光コンテンツの造成についてはよりインバウンドを意識したような体験事業とか、中々、足を運んでいただけない場所の魅力をどういうふうに商品造成につなげていくかとか、もう少し具体的にインバウンド向けに販売できる商品造成というものを企図したいと思っています。
日本経済新聞 では、MICE推進室がやるけれども、必ずしもMICEのためだけではなくて、一般の外国人観光客を呼ぶ、そういったことにも役立つコンテンツを作りたいと、そういうことでしょうか。
市長 はい。
共同通信 空き家の活用に向けたプッシュ型伴走支援ということで、人口減少が顕著な地区をモデル地域とするというふうに書かれているんですけれども、これは具体的にどこにするかとかは決まっているんでしょうか。
市長 今のところ、ここというところを決めているわけではありませんが、今までもそういう地域を中心に空き家の状況について調査しておりますので、そういう中から選定したいと思います。
読売新聞 おおつアプリのところで伺いたいんですけれども、先程市長は避難所とかでの活用を一つ例のとして挙げられていたかと思うんですけれども、これを日常的に市民の方が活用できるような場面を何か想定されているのかということと、マイナンバーを活用するというところで、マイナンバーの普及率アップも含めて何か関連するような施策を考えられているのか、その辺を伺えればと思います。
市長 現時点の課題として、市民が利用する行政サービスというのは様々分散して、利便性が逆に低下しているような状況がありますので、まずはこのデジタルサービスを統合したいと思っています。仮称ですけれども、おおつアプリを導入することによって、このアプリを使えば大津市の行政サービス、デジタルで受けられるというものにしっかりとコンタクトできるようにしたいと思っていますし、マイナンバーカードを活用することで属性がはっきりしますので、その属性に応じたきめ細かい情報提供などもできるようになると期待しています。
時事通信 フリースクールの関係でお尋ねしたいんですが、今回新規事業を3つ新設するということで、特に1つ目、2つ目、スクラム会議のメンバーということで、スクラムという言葉もキーワードかと思うんですけれども、他の民間施設との連携であったり、横並びの連携も含めて、フリースクール支援に対する市長の考え、狙いをお聞かせいただけますでしょうか。

市長 フリースクールを支援するというよりも、フリースクールとの連携を深めていきたいと思っています。学校現場のみならず、先程ご説明を申し上げたウイングというものを小学校3カ所、中学校3カ所、これは校外に持っています。
そして、今新たに校内の「校内ウイング」ということで、自分の教室には入れないけれども、学校の他の教室で過ごすと、こういった居場所を色々作っているわけですけれども、やはりフリースクールもその選択肢の中で大きな位置を占めておりますので、フリースクールの皆さん、フリースクールのみならず、民間団体の皆さんとの連携を深めることによって、さらに子どもたちの状況、そして子どもたちの支援というものを、手を携えてやっていきたいという思いで、幾つか事業を建て付けたところです。
NHK おおつアプリの避難所受付アプリについて伺いたいんですけれども、具体的にはチェックインをすることできめ細かい支援物資とかを避難所に運んでいくとか、そういうような流れになるんですか。運用としてどのようなことを考えているんでしょうか。
市長 一例として挙げたところなので、これから詳細の検討をしますが、既に先行自治体で実証実験をしている例から申し上げますと、避難所に誰が避難をしたのかということを、今は紙で把握をしようとしています。このアプリを使うことによって、避難所に避難した方がスマートフォンをかざすだけで、誰がどこにチェックインし、避難したのかということが分かるようなシステムが構築できると聞いておりますので、こういったものも災害に強いまちづくりに寄与するのではないかと期待しています。
NHK 大津市役所とかで把握する人がいて、そこから指示を飛ばしてという流れですか。
市長 先程も申し上げたように、このおおつアプリはマイナンバーカードと連携しておりますので、このアプリによって個人情報がしっかりと把握できるようになっています。ですから、スマートフォンをかざすと、どこの避難所にその方が避難したのかということが、その避難所において把握ができるということです。
NHK 自走式トイレカーですけれども、これは具体的にどういうような大きさのトイレとか、何台ぐらい用意するとか、何か考えていらっしゃるのでしょうか。
市長 中型のものを2台購入しようと思っています。
NHK 災害が発生したとき、具体的にどういうところにこの車を持っていこうと思っていたりしますか。
市長 市内で有事の際には、やはり避難所の快適な運営ということからすれば、まず避難所に派遣することになると思います。
NHK 全体というか災害関連で、トイレカーとかおおつアプリとかの導入をされるということで、具体的に災害について、大津市として今後どのように取り組んでいきたいとか、お考えがありましたら教えてください。
市長 まず、説明の中でも申し上げたように、公共施設で耐震性能を確保していく取組をしていかなければいけないと思っています。具体的に申し上げれば、中消防署は昨年12月から運用を開始しましたけれども、未だこの市役所本庁舎においては耐震性能を有していない中で、今も執務を続けている。いついかなる災害が来るとも限らない中で、やはり速やかに対応しなければいけないと思っていますので、令和7年度中に庁舎整備の基本計画を策定することとしています。それと同時に、それぞれの地域における避難所の機能向上を図っていかなければいけないと思っておりますので、先程の説明の中にもありましたように、例えば中学校の体育館の空調設備の整備とか、こういったトイレカーをはじめとした新たな備品の導入、そしておおつアプリも災害にしっかりと活用できるということで、採用を決めたところでありますので、こういったものを重ね合わせながら、総じて災害に強いまちづくりを進めていきたいと思います。











更新日:2025年03月07日