社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
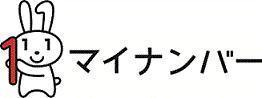
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票のあるすべての方に1人に1つの番号を付番して、国や都道府県・市町村の行政機関などが各々に保有している社会保障、税、災害対策に関する分野の個人情報を同一人の情報として効率的に把握する仕組みです。各機関で保有する個人情報は情報提供ネットワークを介して情報連携することになり、住民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現、行政の効率化ための社会基盤(インフラ)となる制度です。
マイナンバー制度が始まると
住民票のあるすべての方が1人ずつ重複の無い1つの個人番号(12桁)を持つことになります。個人番号は漏えいにより不正に使われるおそれがある場合を除いて、原則変更されません。
住民の利便性の向上
住民の方が、国や都道府県・市町村の行政機関などの窓口で社会保障・税・災害対策に関する手続きを行う際に個人番号カード等を提示し、書類に個人番号を記入することで添付する証明書等がこれまでより少なくなります。
また自宅のパソコン等から行政機関などが保有している自分の情報を確認したり、行政機関などから様々なサービスのお知らせを受け取ったり、行政機関などへの手続きを電子的に済ませることができるようになります。
公平・公正な社会の実現
国や都道府県・市町村の行政機関などが、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、行政サービスを必要としている方にきめ細やかな支援を行うことができます。また不当に負担を免れることや不正受給を防止します。
行政の効率化
国や都道府県・市町村の行政機関などで、情報の照合、転記、入力などに要する時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務間での情報連携が進み、それぞれの行政機関などで行っている作業の重複などが削減され行政事務の効率化が図られます。
マイナンバー制度導入後のロードマップ(案)
マイナンバー制度導入後のロードマップ(案) (PDFファイル: 342.7KB)
平成27年10月~
マイナンバーの通知
住民票のあるすべての方に住所あてに「通知カード」が送付されます。通知カードは券面に氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載された紙製のカードとなります。
(注意)通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。詳しくは下記ページをご覧ください。

平成28年1月~
個人番号(マイナンバー)カードの交付
交付申請手続きをされた方にマイナンバーカードを交付します。
券面に氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載された顔写真付きのICカードとなります。
本人確認のための身分証として利用できるほか、ICチップの電子証明書の機能を利用した公的個人認証サービスにより、自宅のパソコンからインターネットでe-Taxなどの電子申請を行ったり、全国の所定のコンビニエンスストアから住民票の写しなどの証明書の交付を受けることができます。

平成28年1月~
マイナンバーの利用開始
法律や条例に定められた社会保障・税・災害対策に関する手続きでの利用が始まり、個人番号カード等を提示し、書類の一部に個人番号の記入が求められます。
- 社会保障関係:年金、雇用保険、健康保険、生活保護、児童手当、障害者手帳など
- 税関係:確定申告書、源泉徴収票、扶養控除、支払調書、法定調書など
- 災害対策関係:被災者生活再建支援金の支給など
平成29年1月~
マイナポータル(情報提供等記録開示システム)の利用開始
マイナポータルは、国が構築、運営するオンラインサービスです。
情報連携の開始に伴い自分の情報を行政機関がいつ、どことやり取りしたかの履歴確認や、行政機関が保有する自分に関する情報、行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等からポータルサイトで確認できるようになる予定です。
本格運用に先立ち、アカウント開設を行うことができます。
平成29年11月~ 情報連携の本格運用を順次開始
行政機関間の情報連携の試行運用開始
国・都道府県・市町村等の情報連携が始まります。申請を受けた行政機関などが関係各機関に照会を行うことで情報を取得することが可能となるため、役所の窓口でも社会保障・税・災害対策に関する手続きを行う際に提出する書類が簡素化されて少なくなります。
個人情報の管理体制
個人情報を特定の機関に集約して一元的に管理を行うことはありません。
各々の行政機関等で保有している個人情報を法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の業務で利用が認められる範囲で他の行政機関等と情報連携します。
情報連携は個人情報を暗号化したうえで国が構築する専用の情報提供ネットワークを利用します。また個人番号を取り扱う従事者が個人情報を正当な理由も無く他人へ提供したり、何人でも他人の個人番号を不正に入手すると処罰の対象となります。
特定個人情報保護評価(PIA)
マイナンバー制度の導入に伴い、個人番号をその内容に含む個人情報(特定個人情報)を保有する事務については、特定個人情報を保有するまでに、特定個人情報の保有・利用に伴って生じるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置等を、特定個人情報保護評価書により公表することとされています。
この一連の手続きを「特定個人情報保護評価」といいます。
本市でも評価対象となる事務について特定個人情報保護評価を行い、特定個人情報保護評価書を国の個人情報保護委員会に提出して公表を順次行っています。
個人情報保護委員会のホームページより評価実施機関名を「滋賀県大津市」とすることで検索が可能です。
独自利用事務
本市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、同法第9条第2項に基づく条例を定めています。
また独自利用事務のうち、個人情報保護委員会で定める要件を満たすものについては、同法第19条第8号により情報提供ネットワークシステムを利用した他の行政機関等との情報連携が可能とされており、次のとおり個人情報保護委員会に届出(個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行い、承認されています。
大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
執行機関【市長】
執行機関【教育委員会】
| 届出 番号 |
独自利用事務の名称 | 根拠規範 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの (PDF:147.2KB) | 大津市就学援助費給付要綱 (PDF:310.6KB) | 教育委員会 学校教育課 |
| 2 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に準じて実施する特別支援学級への就学等のため必要な経費の支弁に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの (PDF:147.6KB) | 大津市特別支援教育就学奨励費給付要綱 (PDF:186.5KB)
平成29年4月1日改正 |
教育委員会 学校教育課 |
マイナンバー制度について
詳しくは、デジタル庁の「マイナンバー(個人番号)制度」のホームページをご覧ください。
お電話でのお問合せ先
マイナンバーコールセンター
平日9時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
日本語窓口
0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
050-3816-9405(IP電話)
外国語窓口
0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
注意:英語対応
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 情報政策課
〒520-0037 市役所第2別館
電話番号:077-528-2713
ファックス番号:077-522-9300
情報政策課へメールを送る










更新日:2025年08月29日