防災知識集 風水害編
台風とは
台風の定義
台風とは、赤道付近の海上で積乱雲の群が渦を巻いて発生した「熱帯低気圧」のうち、中心付近の最大風速が17メートル毎秒を越えるものを台風とよびます。
1番多く発生するのが8月、次いで9月、7月の順であり、特に9月の台風は強いものが多く、夏から秋にかけては日本本土に上陸し、大きな被害をもたらすような台風が多い時期となります。
台風の風
台風の風は北半球では、台風が左巻きのうずまきになっているため、台風の風力は、進行方向にむかって右半円(東側)が左半円(西側)よりも強く、左右で平均風速が10メートル以上も違うことがあります。
このため、台風のコースに近い進行方向右側(東側)の地域では、強い暴風雨に見舞われ、大きな被害が起こりやすくなるため、より一層の警戒が必要となります。
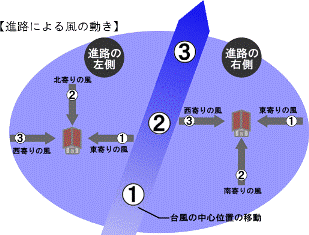
風速とは
風がふき、過ぎて行く速さをm/秒(メートル毎秒)単位であらわしたものです。
風のふきかたは一様ではないので前10分間の平均をとった速さを平均風速、瞬間の風速を瞬間風速といいます。
単に風速という場合、一般的には平均風速を指します。
- 風速10m/秒(10メートル毎秒) 大きな枝が動き、傘が差しにくくなる。
- 風速15m/秒(15メートル毎秒) 看板やトタン板が飛び始める。
- 風速20m/秒(20メートル毎秒) 小枝が折れる。上体を傾けないと風に向かって歩けない。
- 風速25m/秒(25メートル毎秒) 瓦が飛び、テレビアンテナが倒れる。
- 風速30m/秒(30メートル毎秒) 雨戸が外れる。家が倒れることもある。
風向と風速の関係について
風向とは、空気の流れで風の吹いてくる方向をいい、1秒間に風が吹き抜けていく距離をメートルの単位で表したのが風速です。
風向も風速も観測時の10分間の平均値で表すことになっています。また、平均値でない風速は瞬間風速と呼んで区別しています。
ちなみに、日本で記録された最大風速は、昭和40(1965)年9月10日の台風23号のときに、高知県室戸岬で観測された毎秒69.8メートルです。
最大瞬間風速は、昭和41(1966)年9月5日の第二宮古島台風(台風18号)のとき、沖縄の宮古島で観測された毎秒85.3メートルでした。
話は少し横道にそれますが、天気図に使われている手金記号には、羽矢根型の尾が付いていますが、これは風向と風力を表すものです。
風向は16方位をもって表し、風力は0~12までの13段階に分類した「ビューフォート風力階級」によって表します。例えば、風力6とは毎秒10.8~13.8メートル未満の風速を表しています。
このように、風速と風力とは、それぞれ異なるものです。
雨の強さと降り方
強い雨が降ったり、それほど強くない雨でも長時間降り続いた場合には、洪水や土砂災害のおそれが高まります。 気象情報などをよく聞き、災害が起こる前の情報収集をしっかり行いましょう。
やや強い雨 1時間雨量が10~20ミリ未満

- 人の受けるイメージ:ザーザーと降る
- 人への影響と屋外の様子:地面からのはね返りで足元がぬれる
- 災害の危険性:この程度の雨でも長く続く時は注意が必要
強い雨 1時間雨量が20~30ミリ未満

- 人の受けるイメージ:どしゃ降り
- 人への影響と屋外の様子:傘をさしていてもぬれる。車の場合、ワイパーを早くしてもみづらい
- 災害の危険性:側溝や水路、小さな川があふれ、道路冠水のおそれがある。小規模のがけ崩れのおそれがある
激しい雨 1時間雨量が30~50ミリ未満

- 人の受けるイメージ:バケツをひっくり返したように降る
- 人への影響と屋外の様子:道路が川のようになる
- 災害の危険性:山崩れ、がけ崩れが置きやすくなり、危険地帯では避難の準備が必要
非常に激しい雨 1時間雨量が50~80ミリ未満

- 人の受けるイメージ:滝のように降る
- 人への影響と屋外の様子:傘はまったく役に立たなくなる。水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる
- 災害の危険性:土石流が起こりやすい多くの災害が発生する。
猛烈な雨 1時間雨量が80ミリ以上

- 人の受けるイメージ:息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感じる。
- 人への影響と屋外の様子:傘はまったく役に立たなくなる。水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる
- 災害の危険性:雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要。
自宅の安全チェック表(風水害編)
災害が起こってからでは遅いです。台風などが来る前に、家の周りに飛ばされそうなものや危険なところがないか確認しておきましょう。
| 点検項目 | 点検内容 | チェック |
|---|---|---|
| 雨戸や窓の補強 | ひび割れ・窓枠のガタツキはないか? また、強風による飛来物などに備えて、外側から板で塞ぐなどの処置を行いましょう。 | |
| 鉢や植木、物干し竿 などが飛ばされないように | 飛散の危険が高い物は室内に入れましょう。 | |
| 排水溝の整備 | 落ち葉や土砂が詰まっていないか点検しておきましょう。 |
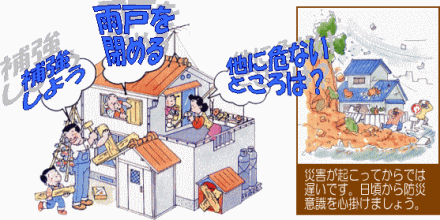
台風や大雨のときは
風や雨の状況によっては、避難が必要となる場合があります。 避難に備えて、準備をしておきましょう。
(1)安全な避難所の確認
家族で避難する避難所を決めておきましょう。避難所まで安全に通行できるかを確認しておきましょう。

(2)非常持ち出し品の事前準備
すぐに避難できるように、最低限必要なものを早めに用意しておきましょう。停電に備え、懐中電灯も用意しておいてください。

(3)正確な情報収集と早めの行動
ラジオ、テレビなどで情報を確認し、危険を感じたら早めに行動しましょう。
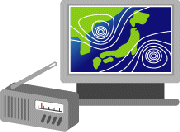
避難情報の種類とみなさんの行動
災害の危険性が高まったとき、市から避難情報が発信されます。市から発表される避難情報は3種類あります。発表をよく聞いて、適切な行動をとってください。

危険な場所から高齢者等は避難

危険な場所から全員避難
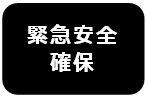
命の危険
直ちに安全確保!
避難のときに注意すること
避難する途中にも危険がたくさんあります。 次のようなことに気をつけ、安全な避難を心がけましょう。
(1)車は使わず歩いて避難
あらかじめ決めておいてた、よく知っている避難コースを通りましょう。
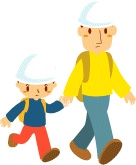
(2)危険なところは避ける
塀ぎわ、狭い道、がけや川のそばは避けましょう。
垂れ下がった電線には触れないようにしましょう。
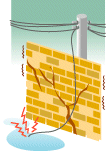
(3)協力して避難
高齢者、子ども、病人、障害者を優先して避難しましょう。
隣近所で助け合いましょう。
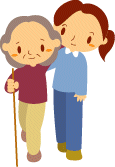
(4)勝手な行動はしない
消防団、地域リーダー、市職員の指示に従いましょう。

こうなる前に避難してください「大雨 ・洪水の中を避難する場合について」
万が一、大雨・洪水の中を避難する場合は次のようなことに気をつけて、安全に避難してください。
足元に注意
水中のマンホールや溝に注意し、長い棒を杖代わりにして確認しましょう。長靴は危険!運動靴で!!

ロープにつながって
小さい子どもなどは大人とロープで体をつなぎましょう。

水深が浅くても危険
流れが速くなると浸水深が浅くても危険です。











更新日:2021年06月22日