議員提案条例・計画
大津市議会において、これまでに議員が提案して制定された条例および策定した計画、議論内容を紹介します。
条例・計画
大津市議会意思決定条例
議会は、合議制機関である性格上、意思決定に時間を要します。現状、そのほとんどを本会議において「議決」していますが、迅速な対応を求める市民ニーズや行政の効率化に対応するために、事象にあわせて「議決」「議長が決定」「議会運営委員会での決定」の3段階に分類整理して意思決定します。
条例制定の意義
- 議会の意思決定方法の明確化
法には議会の意思決定を求める表記として、「議決」以外に「議会は~できる」「議会の同意を得て」「議会の承認を得て」「議会の意思を聞いて」などがあります。
議決以外については、どのような方法によって議会の意思とするのか、市民に明示する必要性があります。
- 議会の意思決定の迅速化
「議決」「議運決定」「議長決定」の3段階に事象を分類整理し、条例化して予め議決しておくことによって、意思決定権限を委任し、機動的な意思決定を実現します。
大津市議会意思決定条例 (PDFファイル: 178.6KB)
がん対策推進条例
市民への意識啓発としてがんの予防、早期発見を推進するとともに、がん対策に取り組む行動理念を示し、地域のがん医療の水準向上を図り、市民が安心して暮らせる社会を実現することを目的としたがん対策推進条例を平成28年3月に制定しました。
条例制定の背景
今や、がんは誰もがかかる可能性のある病(やまい)となっています。しかし、定期的な検診の受診及びがんの早期発見・早期治療により、がんによって亡くなる方の数を大幅に減少させることも可能です。市民、保健医療関係者、事業者、教育関係者、そして市及び議会が一体となってこれらの意識の普及、がん患者等に対する支援の充実、さらには、がんになっても安心して暮らせる社会の構築を目指して、制定しました。
条例の特徴
- 市議会の責務を明記
市議会は、がん患者をはじめとする市民の声を反映したがん対策に関する施策が推進されるよう、市をはじめ関係機関等と連携しなければならないとしました。
- がんの予防の推進及びがんの早期発見について
施策を詳細に明記し、実効性を担保しました。
- 事業者と教育関係者の役割を明記
事業者については、がんに関する正しい知識の普及啓発やがん検診の受診勧奨に努めるとともに、がん患者やがんの経験者に対して理解ある社会づくりの促進を目的として、治療及び家族の看護を行いながら勤務を継続できる環境整備等に努めるとしました。
教育関係者の役割については、保護者とともに学校と家庭が連携してがんに対する正しい知識の習得のため、適切な指導を行うように努めるとしました。
- 市のがん対策に関する計画策定の義務づけ
条例に掲げる内容を実現、計画的に推進されるように、計画策定を義務づけました。
条例の検証
令和4年10月、教育厚生常任委員会にて、執行部が認識する当該条例の課題、条例に基づく施策・事業等の実施状況・課題等を確認の上、条例改正や運用改善の必要性などの協議を行い作成された検証結果報告書が市長に提出されました。
がん対策推進条例検証結果報告書(令和4年10月) (PDFファイル: 224.0KB)
大津市がん対策推進条例 (PDFファイル: 177.5KB)
議会基本条例
議会運営の基本理念や基本原則、議会と首長との関係などについて定め、二元代表制の下、議会の役割や責務、住民自治の実現のために議会が何をすべきかについて示した、議会基本条例を策定しました。(平成27年4月制定)
策定の経過
議員で構成する政策検討会議で議論し策定したもので、大津市議会がこれまで進めてきた改革の集大成と位置付けており、その内容を条例に明文化し、これまでの歩みを後退させないための市民との約束として制定しました。
条例の特徴
- 議会に関する条例を一本化
議員定数条例など、個々に規定されていた条例を整理統合し、分かりやすいものとしました。
- 災害時の議会の行動基準を明記
議会BCPに基づき、災害時においても議会の機能が維持できるように定めました。
- 市長等に意見陳述の機会を付与
議会からの条例の提案や議案修正に対し、市長等は意見陳述ができるようになりました。
- 政策検討会議と大学とのさらなる連携
議会からの政策立案の条例などを策定するため、政策検討会議で議論します。そのために、大学の専門的知見を活用し、議会及び議員の政策形成能力を強化します。
- 「議会局」を設置
議会の政策立案機能を強化するため、それに相応しい体制の充実・強化を図ります。
議会基本条例は、地方議会の憲法といえるもので、議会に関する基本的事項を定めるものです。
議会に関する他の条例等の上位に位置し、自治体における議会の位置付けや責任を明確化する中心的役割を果たします。
大津市議会基本条例(令和元年9月改正) (PDFファイル: 192.7KB)
大津市議会基本条例(逐条解説) (PDFファイル: 495.7KB)
条例の検証
令和6年度、大津市議会におけるこれまでの議会改革の取組の検証に係る政策検討会議にて検証を実施しました。
大津市災害等対策基本条例
平成25年度に作成された議会BCPを踏まえ非常時における議会の役割を明確にするとともに、より災害に強く安心して安全に暮らせるおおつのまちを目指して、より実効性のある「大津市災害等対策基本条例」を策定しました。
条例制定の背景
平成22年3月に、市の防災対策のほか、市民や事業者の皆さんが自分たちのまちを守るために何をすべきかを定めた「大津市防災対策推進条例」を制定し、災害に強いまちづくりを目指してきました。
しかしながら、近年多発する集中豪雨などによる自然災害への対応のほか、大規模事故などのリスクに対する危機管理や被害を少なくする減災の考え方が必要となってきました。
条例制定の特徴
この条例は、予防から復旧、復興、さらにはまちづくり、被災地支援まで広範囲にわたって取り組むべき事項を総合的に明記しています。その特徴は、まず平成26年3月に議会が策定した議会BCP(業務継続計画)を踏まえて、議会の責務等を明記し、「議会の関係性」を明確化したところです。次に、大規模な事故や新型インフルエンザ等の感染症などのリスクに対する「危機管理」や被害の未然防止に加えて被害を少なくする「減災の考え方」を新たに加えたところです。さらに「男女の特性や能力を生かす観点」について条例の基本的な考え方としたことです。また、これまでの災害の検証や教訓から、防災教育の充実、防災リーダー等の人材育成の充実・強化により、地域防災力の更なる向上を図るところです。
条例が目指すまちづくり
いつ何時、いかなる災害に見舞われるか予測することは極めて困難です。しかし、災害に備え被害を防ぎ、低減することは可能です。
災害が発生した時には、行政による「公助」はもちろん、自分の身は自分で守る「自助」、身近な地域で支えあう「共助」が大きな力となります。私たちは、自助、共助、公助の基本理念のもと、これまでの取組みに加えて市民、事業者、市及び議会がそれぞれの責務と役割を果たすとともに、その連携・協働による地域防災力の向上をもって、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指します。
条例の検証
令和4年10月、総務常任委員会にて、執行部が認識する当該条例の課題、条例に基づく施策・事業等の実施状況・課題等を確認の上、条例改正や運用改善の必要性などの協議を行い作成された検証結果報告書が市長に提出されました。
災害等対策基本条例検証結果報告書(令和4年10月) (PDFファイル: 260.0KB)
検証結果報告書に係る対応状況調書 (PDFファイル: 239.8KB)
令和4年12月、検証結果を受けて条例を一部改正しました。
災害等対策基本条例の一部を改正する条例の制定について (PDFファイル: 65.0KB)
大津市災害等対策基本条例 (PDFファイル: 252.7KB)
大津市子どものいじめの防止に関する条例
おおつの宝である子どもたちの将来のために
条例制定の背景
いじめを受けた市内の中学生が、平成23年10月に自ら命を絶つという異例の事態が起りました。市議会では、この事案の発生を受け、二度とこうした悲しい事案が起こることのないよう、大津の宝である子どもたちの将来のため、大津市では、いじめの根絶に向けた総合的な取り組みを社会全体で進めるために、「大津市子どものいじめの防止に関する条例(以下「条例」という。)」を制定いたしました。
条例の策定結果
条例は、各会派の代表者10名で構成する政策検討会議において、平成24年7月から平成25年2月までの間に延べ17回の会議を行いまとめたものです。10名の委員が大きな視野と心をもって、多様な意見に真摯に耳を傾け、非常に熱心に、大津の宝である子どもたちの将来のために、子どもをいじめから守るために、自らの考え・思い・願いを熱く語り、時には、厳しい議論を戦わす中、それぞれの委員が全力を傾注し、策定したものです。(条例は、議会運営委員会における了承の下、平成25年2月市議会定例会に議員提案)
条例の特徴
条例は、単に施策の基本方針を掲げただけの理念条例ではなく、いじめ防止のための政策課題に対して、行政だけではなく当事者である子どもを含めた全ての関 係者の責務や役割を行動規範として規定するとともに、具体的な施策と財政的措置を明記したところに、特徴があると考えております。
子どもの役割
この条例の最大の特徴は、「子どもの役割」を明記したところです。いじめの防止は、子ども自らが、いじめのない明るい学校にしていこうとする主体性も大切 なことであり、いじめにあった場合や友達のいじめを発見した時には、勇気をもって相談してほしいと考えています。その勇気が自らを救い、大切な友達を救う ことになると考え、子どもの役割を規定したものです。
今後の取り組み
市議会では、この条例がいじめの根絶に向けた取り組みの根幹として、大きな効果があるものと期待しており、いじめの防止に向けた取り組みが適正に執行されるよう確認していきます。
条例改正案の検討について
平成25年4月に議員提案条例として制定された本条例ですが、平成27年2月通常会議において執行部より改正案が示されたことを受け、市議会としてあらためて政策検討会議を設置して、改正案について協議・検討を行いました。
結果、大津市子どものいじめの防止に関する条例検討特別委員会を設置、執行部改正案に対して、議員修正案を提出し、これを可決しました。
条例の検証
令和4年10月、総務・教育厚生常任委員会連合審査会にて、執行部が認識する当該条例の課題、条例に基づく施策・事業等の実施状況・課題等を確認の上、条例改正や運用改善の必要性などの協議を行い作成された検証結果報告書が市長に提出されました。
子どものいじめの防止に関する条例検証結果報告書(令和4年10月) (PDFファイル: 324.0KB)
検証結果報告書に係る対応状況調書 (PDFファイル: 286.1KB)
大津市議会議員政治倫理条例
議員が市民の代表として市政に携わる責務を深く自覚するとともに、市民の信頼を得るために倫理基準を遵守し、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的として制定しました。
条例の策定に当たっては、市議会の全会派から選出された議員10名で構成する「大津市議会政策検討会議」において議論しました。
策定の経過
大津市議会では、平成23年2月市議会において、全会一致で「政治倫理の確立に関する決議」を行っており、この条例はこの決議を具現化したものです。
政治倫理の確立に関する決議 (PDFファイル: 41.3KB)
大津市議会議員政治倫理条例 (PDFファイル: 159.7KB)
条例の概要
(前文)
大津市議会が目指している市民に開かれた議会づくりは、議員と市民の揺るぎない相互の信頼関係があって初めて実現できるものである。
そのためには、議員は市民の代表であることを自覚し、市民の負託に答え得る強い使命感と自ら考える明確な政治倫理基準にも続き、公明正大な姿勢の維持及び発展に努めるとともに、誇りと自信をもって市政を担いつつ、説明責任を果たしていくことが必要である。
この条例の下に、議員が誇りを持って市政を担いつつ、市民に説明責任を果たし、市民から一層信頼される議会づくりに努めていきます。
大津市議会議員政治倫理条例の概要 (PDFファイル: 178.3KB)
条例の検証
令和4年12月、議会運営委員会にて検証を実施した結果、条例を一部改正しました。
市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について (PDFファイル: 51.7KB)
令和7年3月、大津市議会におけるこれまでの議会改革の取組の検証に係る政策検討会議にて検証を実施した結果、条例を一部改正しました。
市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例の制定について (PDFファイル: 82.7KB)
審査請求
政治倫理審査会
大津市議会議員政治倫理条例第4条第1項の規定に基づく審査請求があった場合、同条例第5条第1項の規定に基づき政治倫理審査会を設置し、審査を行います。
(設置実績)
・平成25年8月7日設置
・令和5年10月27日設置
審査の結果等の公表
令和5年9月22日付けで、市議会議員から審査請求書が提出されたことを受け、同年10月27日に大津市議会政治倫理審査会が設置されました。大津市議会議員政治倫理条例第3条第5項の政治倫理基準に違反する行為の存否について公正かつ慎重に審査が行われ、その審査結果が議長に報告されました。
この記事に関するお問い合わせ先
議会局 議事課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2640
ファックス番号:077-521-0409
議会局 議事課にメールを送る
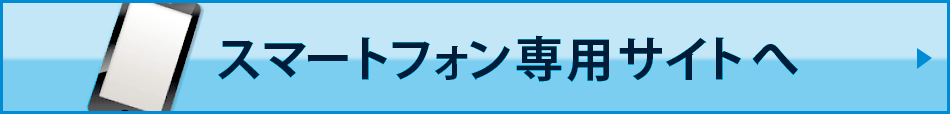


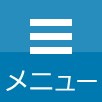
更新日:2025年03月25日