ワークブックの答えとてびき
全部で10問ありました。問題を振り返りながら復習してみましょう。
1 市議会で決める市のきまりごとを何というでしょうか。これを定めることを制定といいますね。
(1)憲法 (2)法律 (3)条例
答え (3)条例
憲法は、国の基本的なあり方を定めるもので、すべての法律やきまりは憲法にもとづいています。日本の憲法を「日本国憲法」といいます。
2 市議会では、市役所の仕事を進めるうえで必要なことを決めますが、それを次の中から選んでください。
(1)予算だけ (2)税金だけ (3)予算と税金の両方
答え (3)予算と税金の両方
予算は、市の1年間の収入と支出の見積もりのことです。住民や会社が税金を納めることで、市の収入になります。支出はその税金の使い道ということです。
3 大津市議会の議員の人数は38人ですが、そのうち女性の議員は何人でしょうか。
(1)7人 (2)18人 (3)28人
答え (1)7人
議員の人数は、大津市議会議員定数条例に38人と定められています。令和5年4月23日に行われた選挙では、男性31人、女性7人が当選して議員になりました。
4 議員は選挙で選ばれますが、この選挙に投票できるのは何歳(さい)以上の市民でしょうか。
(1)18歳以上 (2)20歳以上 (3)22歳以上
答え (1)18歳以上
市民のいろいろな意見や要望は、選挙で選ばれた議員によって実現していきます。みなさんも18歳になったら、必ず選挙に行きましょう。
5 市議会の議員になるには、選挙に立候補して多くの市民から選ばれなければなりません。では、この選挙に立候補できるのは、何歳以上でしょうか。
(1)20歳以上 (2)25歳以上 (3)30歳以上
答え (2)25歳以上
市議会議員の選挙のほかに、いろいろな選挙があります。その種類によって、立候補できる年齢(ねんれい)が違います。
市議会議員、県議会議員、衆議院議員(国会議員)、市長 → 25歳以上
参議院議員(国会議員)、県知事 → 30歳以上
6 選挙で選ばれた市議会議員が、活動する期間は何年間でしょうか。
(1)4年間 (2)6年間 (3)7年間
答え (1)4年間
活動する期間を任期といい、市議会議員は一般的に4年ごとに選挙があります。何度も選挙で選ばれることにより、引き続いて議員として活動できます。
7 市議会の代表者である議長は、どうやって選ぶのでしょうか。
(1)市民が選挙する (2)議員の中で選挙する (3)市長が指名する
答え (2)議員の中で選挙する
大津市議会では、毎年5月中ごろに、議長と副議長を決めるために議員の中で選挙しています。
8 大津市議会がある場所は、どこでしょうか。
(1)大津駅の前 (2)大津市役所の中 (3)滋賀県庁のとなり
答え (2)大津市役所の中
市役所の本館3階と4階にあります。市役所の建物は京阪電車の大津市役所前駅の近くにあります。
9 市議会まで行って、話し合いを聞くことを、傍聴(ぼうちょう)と言います。傍聴する時にできないことは、どれでしょうか。
(1)聞いたことをノートに書く (2)おかしを食べる (3)トイレに行く
答え (2)おかしを食べる
おかし以外でも食べ物を食べたり、飲み物を飲んだりできません。
10 傍聴のほかに会議の様子を見たり、聞いたりするには、どんな方法があるでしょうか。
(1)びわ湖放送の番組 (2)ケーブルテレビの番組 (3)大津市議会のホームページ
答え (3)大津市議会のホームページ
大津市議会のホームページの「インターネット議会中継(ちゅうけい)」で本会議の様子を見ることができます。会議中にはライブ中継で、終わった後は録画映像で、それぞれ見ることができます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
議会局 議事課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2640
ファックス番号:077-521-0409
議会局 議事課にメールを送る
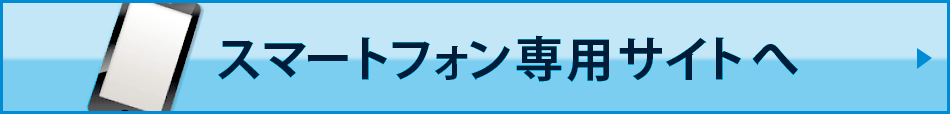


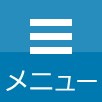
更新日:2024年06月25日